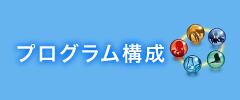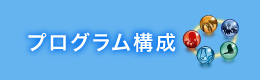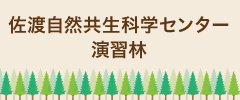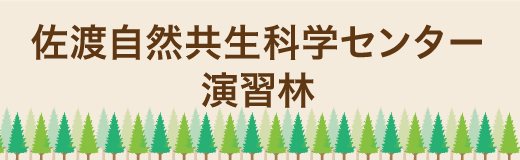フィールド科学教育研究センター
データ駆動型大学附属農場への転換を図り、
農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の共創拠点となる
当センターは企画交流担当および耕地生産担当から構成され、農学部の教員と緊密に連携した教育・研究活動、地域貢献を推進しています。
令和4年3月30日、新潟大学は「デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業」(文部科学省)に採択され、同年4月1日より「フィールドを舞台に農業DXをけん引する高度農業人材育成プログラム」を開始しました。スマート田植機、日本に1台の土壌分析装置、最先端のロボットトラクタ、温室効果ガスのモニタリングシステムなど高度なDX機器を大学附属農場に導入しました。現在は、これらのDX機器を農学部の教育と研究にフル活用して、データサイエンティストの資質を備えた高度農業人材の育成を推進しています。さらに、農業DXに関する産業界等と共創拠点を村松ステーションに形成することに努め、地域の課題解決を図ります。
企画交流担当
農業生産と環境保全に関する教育・研究を推進するために、総合的なプログラムおよびプロジェクトを企画調整しています。特に、地域特有の農業・環境問題を積極的に汲み上げ、農学部と地域社会との交流窓口として情報の収集・管理・発信を行っています。
-

FCシンポジウムの開催
-

五泉市との連携事業 菜の花畑作り
耕地生産担当
【概要】
耕地生産部には村松ステーションと新通ステーションの2 つのステーションがあり、それぞれ五泉市(旧村松町、新潟大学から45km)、新潟市西区新通(新潟大学から3km)に所在しています。村松ステーションは16ha の圃場を有し、食用作物(ダイズ、ジャガイモ)、野菜類(ナガネギ、スイカ、ダイコン)および牧草を作付け、乳牛やヤギを飼育しています。新通ステーションは2.7ha の圃場を有し、水稲を中心に作付けし、転作作物としてタマネギ、エダマメ、ソラマメ、サトイモ、トマト、ナスなどの野菜を栽培しています。一部は施設栽培を行っています。また、春季には草花やハーブの苗生産も行っています。
【教育・研究】
基礎的な農作業体験を目的として、農学部全学生の必修科目である「基礎農林学実習」を両ステーションで開講しています。また、植物生産学・動物生産学・生物生産機械学を専攻する学生の専門的な実習も開講しています。耕地生産担当では、播種から収穫まで、また出産から牛乳生産までの農業生産の全過程を対象にして、環境負荷の少ない持続的農業に関する研究を行っています。村松ステーションでは、農業機械利用による省力生産技術、耕種と畜産での資源循環、資源循環型酪農における乳牛の生産性および繁殖成績について研究しています。新通ステーションでは、気候変動に対応できる水稲新品種の開発、環境に配慮した野菜栽培技術について研究しています。令和4年度より、デジタル技術を活用した先進的な農業機械、計測機器を導入し、データ駆動型大学附属農場への転換を図りながら、農業DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みを推進しています。
【地域連携・社会貢献】
村松ステーションでは、五泉市と連携して、地域中学校の農場実習や児童・園児の農場見学などを受入れているほか、学校給食用野菜を提供しています。新通ステーションでは、園児の農業体験を毎年開催しています。また、大学院における教育プロジェクトの一環として、地域の酒造会社と連携し、新通ステーションで栽培した酒米を原料とする大学ブランドの日本酒‘新雪物語’を造っています。他に、生産物の販売を通して地域との交流を行っています。

農業用ドローンの実演飛行(村松ステーション) 
搾乳実習(村松ステーション) 
可変施肥田植機による水稲機械移植(新通ステーション) 
水稲機械収穫(新通ステーション)
気象および土壌
村松ステーション/平均気温13.2℃、降水量1788㎜、積雪70㎝、標高25m、火山灰黒ボク土壌
新通ステーション/平均気温13.2℃、降水量1770㎜、積雪20㎝以下、標高−1m、信濃川沖積土